よく勘違いされることなんですが、ぼくらはカンボジアでボランティアをしていると思われがちです。
確かに見た目はそうかもしれません。
井戸を掘ったり、道を作ったり、小学校を建設したり。
見た目はそうかもしれないけれど、ぼくらはボランティアでも支援でもない関わり方を選びました。
カンボジアでボランティアする自分は自立しているのか?
カンボジアに小学校を建ててから、何かがぼくの中で引っかかっていました。
「建設しただけでは意味がない」
ということは、学校建設する際に散々言われた言葉です。
「そんなんわかってるわ!」
とは思っていても、実際にどうやって運営されていくのか、子ども達が毎日通うのか、先生はいなくならないか、不安な要素はありました。
何年か経って、壁が崩れたとか、雨漏りがするとかハード面の修繕費だったりとか、どうしていこうって思ったりもしました。
これまでは「カンボジアでこんなことしたい!」「これが必要!」って声をあげれば、助けてくれる人たちが大勢いて、何とかやってこれました。
でも、また何か必要なものが出た時に「今度はこれが必要です!」って言いたくなかったんです。
活動を助けていただいたありがたみは十分に感じながらも、いつまでも困ったら人頼みでは意味がないのだと。
よく「途上国の自立支援」とか言いますが、その言葉通りにするならば、まずは自分がきちんと自立していなくては、何もできないのだということです。
寄付頼みの活動は本質的とは思えなかった
寄付頼みでの活動には限界があって、継続的に活動する算段が立たない時点でとても本質的ではないのだということです。
自分たちに余力がある時は、何でもかんでも作ったり与えたり。
でも、ちょっと余力がなくなると、本当に必要な時にすら必要なものを整えることができない。
これってとても大きな損失だと思います。
なんの?って村人や子ども達からの信頼に関してです。
本当に困っている人の力になりたいのか、それとも手を差し出している自分に満足したいだけなのか。
ボランティアって本当難しくて、小さな親切が時に大きなお世話だったりします。
そんな自分本位な小さな親切が相手の心に届かなくて、相手が期待通りのリアクションをしてくれないと、伝わらないと嘆いてみたり。
そういうのいっぱい見てきました。
どこか押し付けがましいというか、相手の気持ちに寄り添っていない接し方。
それって本当は自分がイイカッコしたいだけじゃないの?
それってイイことしている風な自分に満足しているだけじゃないの?
実績を求めるのか、それとも、成果を求めるのか。
似ているようで、大きく異なるこの両者がたまにごっちゃになって、実績を積み上げることへ固執してしまいそうにもなります。
だけど、とことんこだわりたいのは、「実績」ではなく「成果」で、「何をしてきたか?」よりも、それによって「どうなったか?」なんです。
学校を建てた実績なんかどうでもよくて、学校を建てたことによって、村が、子ども達がどう変わったのかがあって初めて成果です。
だから結局、自分の見え方はどうでも良くて、例え時間をかけてでも、大切にしたものを守れていることが、ぼくにとっての成果の基準。
その選択や決断が、本当に正しいのか迷う時もあるけど、何が正しいかなんてわからないし、相手の気持ちに寄り添っていれば、自ずと道が見えてくるのだと思っています。
それがイイカッコしたいだけだと、勝手にブレていくんだろうな〜って思っています。
そんなの例え言葉が通じなくても伝わるだろうし、本当の応援なんて生まれないから。
子ども達のために同情で何かしてほしいなんて思いません。
でも、もし子ども達のためにって思ってくれるなら、会いに来てほしいです。
お土産も差し入れも寄付金も何もいらないから。
そしてきっと何かを与えるのではなく、与えられることになるから。
与えるより与えられることの方が多い
ぼくは子ども達と一緒にいて、いろんなものをもらっています。
自分が持ってきたお菓子を分けてくれたり、摘んできた花をくれたり、頑張って覚えたアルファベットを使って間違いながらも書いてくれる手紙だったり。
ここにあげた例は目に見えるものですが、それらを通じて本当にぼくがもらっているのは、自分ができることで相手を喜ばせようとしてくれる気持ち。
さりげない優しさが一時的なものではなく、いつ行ってもそうだから、人生の中で大切なことは教えなくてももう知っているんだなって思います。
だからぼくらが変に何かを与えたりするお節介のしすぎで、子ども達の優しさが計算されたものになってしまわないようにしたいです。
自分のできる何かで人を喜ばすことができることができる。
このまんまのみんなでいてほしい。
そんな子ども達のこと、ぼくは尊敬しています。
避けられないカンボジアの子ども達の現状
ただ唯一、避けられない現実として起こりうる可能性のあるお金の問題。
何かに夢中になりたい時に「お金がないからできない」とは言わせたくないから、この子達のこと絶対守らなきゃって思っています。
その実現がボランティアとか支援って関わり方だと、寄付頼み、里親頼みになるのかもしれません。
でも、ぼくらは血は繋がっていなくても家族だから、そんなピンチが来ても一緒に乗り越えて行こうって話をしています。
まだまだやんちゃで甘えん坊な6歳の子ども達と。
そしていつ訪れるかわからないピンチが来てから「どうしよう」って悩むのではなく、そうなってから頭を抱えなくていいように今一緒に考えようって。
だから、いつ何が起きても家族が離れ離れにならないように、家族の一員が気兼ねなくやりたいことに突っ走っていけるように、日本からやって来た血の繋がっていないお父ちゃんは未来貯金を始めました。
いつでも変わらず優しさを分けてくれる子ども達がいるのに、父ちゃんの優しさは気まぐれだったなんて言わせないために。
いつまでもこの子達と笑っていられるために、ぼくらは共に生きていくって方法を選びました。
みらいスクールをきっかけに生まれたぼくら家族の物語はまだまだ始まったばかり。



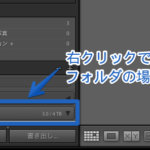




















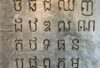











コメントを残す