
個人的に2016年最大のイベント、みらいスクールの開校式が終わって日本へ帰って来ました。
改めて開校式に来てくれた皆さん、ご協力いただいた皆さん、いつも応援してくれている皆さん、ありがとうございました。「これからどうするの?」と聞かれることが多いので、ぼくなりの関わり方をまとめてみました。カンボジアの農村部に建った小学校の物語の始まりです。これからも一緒に見届けてくれると嬉しいです。
ノマドワーク×国際協力でこれからもやっていく
これが現時点での答えです。
WHY ノマドワーク
時間や場所に縛られない働き方ができるからです。建設の時もそうでしたが、建設費用があっても建設現場へ行く時間がなかったら嫌だった。だからどこかに雇われて、決まった日時は出社しなくてはいけない働き方だと、自分がカンボジアに行くタイミングを自分で決められないからです。
何をするのか?
具体的にはまだ決まっていませんが、子ども達と協力しながらやっていけるといいなと思います。何かあった時に、一方的にお金を出すのもおかしな話だし、ぼく自身も寄付頼みになる活動はしたくないからです。
- 子ども達の将来に繋がりつつ
- 強制や労働ではなく学びながら
- 自分たちの手で自分たちの未来を守る取り組み
抽象度が高すぎますが、またまとまり次第報告します。
スパン
これも具体的には決まっていませんが、今回入学した一期生たちが20歳になることが一つの目処かなと考えています。この子達にはもう物心と言うものがあるだろうし、建設から開校までの期間を通して多くの外国人たちが来たことも記憶に残っているはず。
その子達が大人になった時に「どうだ、俺はすごいだろう肩を揉め」と言いたいのではなく、なぜこれだけの人がこの学校に関わってくれたのか、それを見た君たちは次の世代のために今から何ができるか?みたいな話をつまみに一緒にお酒が飲めたらいいなと思っています。
建設後も関わらないといけないのか
そんなことないです。むしろ公立学校なのでぼくらはここからは部外者です。勝手に校舎に入ったり、勝手に日本語教えたりとかそういうことはできません。「建設した後に責任を取らないならカンボジアに学校を建てるな」と言う人のほとんどは建てたことない人だと思います。建てた後は部外者なので、ぼくらはそっと遠くから見守るだけです。
ぼくなりのノマドワークと国際協力と経緯
もうちょっとぼくなりの視点でまとめておきます。
こうなった経緯
この村ではまだ自分の力を必要とされていると感じたからです。
正直何もなかった原っぱに校舎が立っていく時や、建った後に学校まで子どもを送り迎えすることになったお父さんお母さんを見た時に、この地に長らく続いてきた景色と習慣を大きく変えてしまった気がして「学校を立てたことは本当にこの人たちのためになるのだろうか」とも思いました。
だけど開校式に来てくれた村のみんなの顔を見たら「やったことに間違いはなかった」と思えました。間違いなかったと思えた場で「もうしばらく来ないの?」「困ったら誰を頼ればいいの?」という声が聞こえてしまったら、ぼくは条件反射で「また来るよ」と答えていた。
ぼくなりの国際協力
こういう活動って自分がやりたくてやることだとは思わないんですね。自分たちだけの力では解決できない課題を抱えた人たちが、誰かの力を頼りにしている現状があるから、その現状に合わせてできることをできる範囲でやるというのが、ぼくなりの国際協力です。
活動したいから活動場所探すとか、自分がやりたいことをやらせて支援だ雇用だとかそういうことやりたくありません。
ぼくなりのノマドワーク
必要なことが出た時に、時間もお金も労力も惜しみなくかけられるようにするために、ぼくはこれからもノマドワーカーなスタイルで働きます。カンボジア拠点とか日本拠点とか決めずに、今自分がいるべき場所にいるために。
これからもカンボジアの小学校と関わっていくからといって、住み込みで何かするわけでもないし、言われたからてホイホイやるのもしない。何がどのくらいいつまでに必要かをしっかり話せて見極められて、その中で自分ができる範囲でやる。いざと言う時のためにできる範囲を広げていく。
「ビジネスの先に支援が成り立ち、支援がまたビジネスを加速させる」いつかどこかで聞いたこの言葉の通り、この場所をビジネスの舞台にはしません。ぼくはぼくのビジネスで、この場所を守っていく。
人と手を組む
やってることが別々だけど、共通点があったりお互いの長所を生かしきれそうな人と手を組むと1+1=2以上になるみたいなことを聞いたので、そうします。今回のアイキャッチ画像の後藤勇太です。彼はカンボジアで孤児院を運営してます。お互いのためになる何かができたらいいですね。
まとめ
ということでカンボジアに建設した小学校は日無事に開校しましたが、ぼくはこれからも日本とカンボジアと、たまにその他の国を行ったり来たりしながら、その瞬間瞬間で必要なことをやっていきます。
あまり頭のいい方ではないので、やってみたけど違うなって思ったら違うやり方したりするかもしれませんがその辺は多めに見てもらえたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。
追記:その後のこと
MIRAIブランドが始まりました。
村で誤解されました。
村でのものづくりはやめました。
いろいろ失って感じた本音。





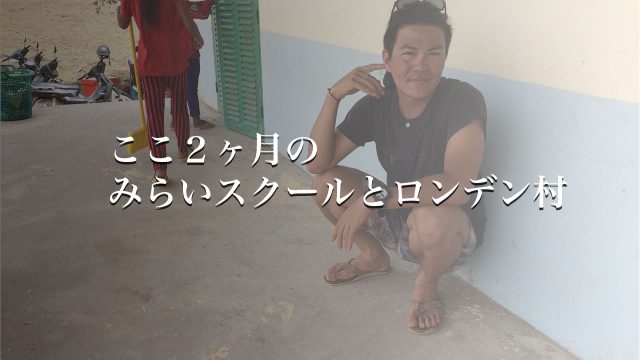





































コメントを残す